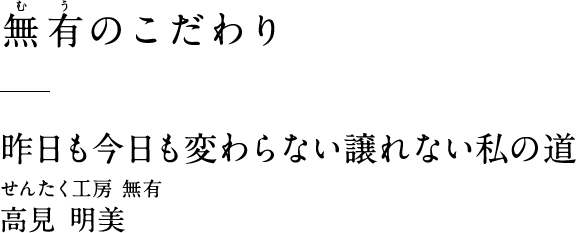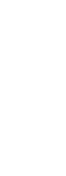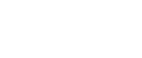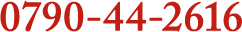心地よい光り輝く朝日を浴びながら、店頭のシャッターをガラガラと開ける。
鳥のさえずる声、そっと、そばにたたずむ日々草の花、行き交う通勤ラッシュの車・・・。
そんな何気ないいつもの朝。
「ああ、生きてる。生きていて良かった。」
と平凡な朝に言いようのない喜びと幸せを感じる。
弊店は、衣類のクリーニング業を営んでいる。
一般のドライクリーニング(以下ドライ)とは違い、安心・安全をモットーに全品水洗いをしている。衣類は、お客様の「皮膚」と考え、ドライ液や化学糊、その他、有害と思われる化学物質を使用していない。還元した水で少量の純固形石鹸を使っての、手洗い手仕上げの健康クリーニングといえる。もちろん環境にも優しい。
このクリーニングシステムを完成するまでに色んな出来事があった。ドライを止め、今のクリーニングに切り替えたのは、平成8年の秋だった。
命がけの取り組みであったと言っても過言ではない。
昭和の高度成長期にクリーニング業を営む両親の元に私は生まれた。父がアイロンがけをする台の上に登り、小さな袖馬にちょこんと座り、大好きな父の側で過ごすのが日課だった。私の顔よりも大きなアイロンをツルツルと滑らせヨレヨレのシャツをあっと言う間に新品のように仕上げる父。魔法使いのような、そんな父の手元を見て私は育った。母も良く働いた。
いつも三角のスカーフで髪をキュッと束ねていたのが印象的だった。母がアイロンがけをする足元で、洗濯かごに入ってよく遊んだ。母を見上げると体全体で軽快なリズムを刻みながらアイロンがけをしていた。そんな母の背中が妙に心地よかった。
私は、高校卒業と同時に結婚し3人の子宝に恵まれた。その頃には、母が体調を崩した事もあり、両親は、すでに高見クリーニング店を閉店していた。
クリーニング業は夏は暑く冬は寒い。
おまけに力仕事で重労働であるため、両親は私に跡を継がせるつもりなど全くなかった。そして、両親の苦労を見て育った私は、「クリーニング屋だけにはなるまい」と強く心に誓っていた。
そんなある日、突然、主人が会社を辞めてきた。唐突にクリーニング業を再開すると言い出したのだ。
もちろん私は猛反対した。しかし、そのかいもなく生活の為仕方がなくそれに流されていった。
当時で四十年ぐらい前の古びたドライ機とアイロンが一丁。最初の月の売り上げは、三万七千円だった。
長女4歳、長男3歳、次男1歳の春、梅の花の便りが聞かれる頃だった。次男を背負い長女と長男の手を引いて「クリーニング御用はありませんか?」と毎晩外交に出た。
とにかく必死で働いた。その日暮らすために、育児、家事、仕事に一心不乱に没頭した。朝起きて猛烈に走り出し、知らない間に足に青あざがいくつも出来ていることもしょっちゅうあった。
全てをこなし、子供たちを寝かしつけて家事を終え、夜中ちかくになってやれやれ、と思った瞬間、空腹が襲いかかってくる。良く考えてみると朝から何にも食べていないことに気づくこともしばしばあった。とにかく、この身体一つで一日二十四時間では全く足りなかったのだ。
その頃は、当然のようにドライをしていた。小さな頃からドライにまみれて育ち、ドライ無しではクリーニング業が成り立たない、という業界や世間の常識に何の疑問も持たずにいた。